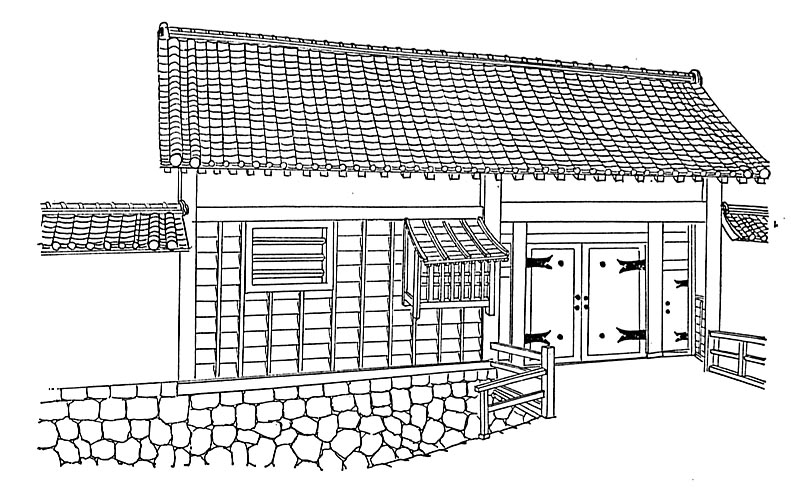
「出て来い、伝五郎。出てこれぬのか臆病者」
興津は犬のようにほえた。
もともと興津の家は、駿河に住し、今川義元、氏真に仕え、今川家亡き後は、関東の北条家に仕えて江戸城を守備し、度々戦功をあらわしている。
興津七郎左衛門の兄の良勝にいたっては、関が原合戦が始まろうとすると、矢もたてもたまらず勝手に家を飛び出して伝をたよって東軍に加わったほどの戦好きであった。
その時良勝は、名を辻と変えて加藤嘉明の手に加わって、なかなかの武功をあらわし、合戦後は水戸の徳川頼房の家臣となった。
昌縄にしてみれば、喧嘩はご法度なのでしたくはない。
だが一人でのこのこ出てゆけば、集団リンチが待っている。
あまり気は進まぬが、虫のようにはいつくばり、激しい暴行を受けようとも、ひたすら額を地面にこすりつけて許しを乞えば、命までは取られないだろう。
また、裏門から逃げ出すという選択もある。
しかし、今逃げてこの身が無事でもこの屈辱は一生残るだろう。
さらに今後、興津らから一層加えられるであろう屈辱をどうしのげばよいのだろうか。
喧嘩がしたいなら1対1で素手でやればよく、人を大勢ひきつれてくる興津の卑怯さは承知のうえではあるが、生真面目な昌縄は、
「臆病者」
という罵声から逃れることができない。
昌縄は相手が大多数であろうが、「臆病者」とののしられてここで戦わなければ、ひい爺様の重継公に申し訳のないような気がした。
ひい爺様の米倉重継公は、戦国武田家にあって武名が高く、合戦では相手が強力であろうが一歩も引かなかったという話を80歳を過ぎたじい様の信継の、すっかり歯の抜け落ちた口から良くきかされた。
「その時はそうよ、ワシが伝五郎位の歳であったさ」
なんでも、信継の話では、武田信玄公が京へ上るべく、元亀3年の三方が原の合戦では、米倉重継公は神君家康公の本陣を蹴散らし、信玄公が深追いせず引き返せといわなんだら、家康公の首はひい爺様の重継公があげていたであろうと、昌縄をきちんと正座させて、講談口調で話すのが大好きだった。
そして、信継は最後に、昌縄が今お禄を頂戴しているのは、ご先祖の武功のおかげだとすこし照れながら結ぶのである。
むろん、「ご先祖の武功」のなかに、戦国生き残りの信継自身も入っている。
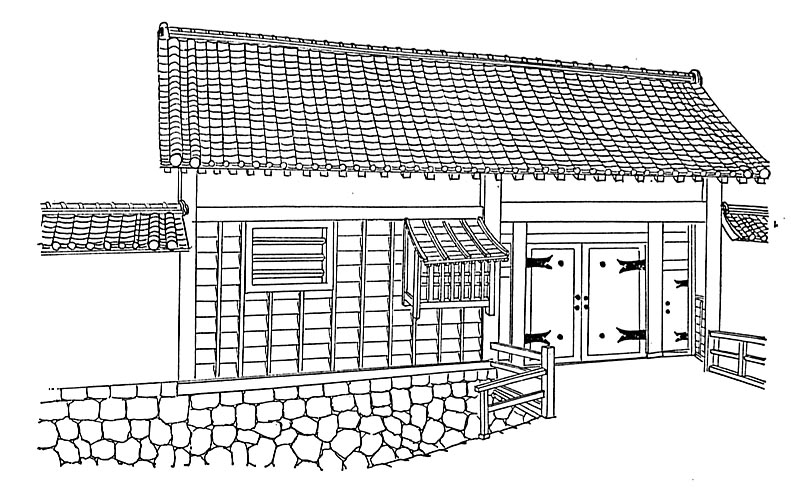
100年に及んだ戦乱の世が終息して、13年がたったが戦に破れた浪人は野に満ちている。
そして、今はおとなしくしているとはいえ、戦国生き残りの大名は油断がならない。
世はまだ緊張し、武断政治が断行されている。
喧嘩両成敗は戦国よりのならいである。
昌縄はことの次第を書き記し、自害の準備をした後、上司の松平内膳正重則に報告した。
お上は当然のことであったが、襲撃側の興津らには厳しかった。
徒党を組んで、騒ぎを起こすのはご法度であり、しかも大勢がかりで昌縄を襲い、逆に返り討ちにあっているのは武士として不甲斐ない。
したがって興津らは死罪となり、土屋市之丞勝正が検使として出向いた。
しかし、興津、江波はその場で死に、内田は重傷を負い、そのまま家にたどりつく前に道路に倒れ死亡した。
残った奥山は裁定を伝え聞き、検使の土屋が来る前に自害した。
一方米倉昌縄は、
「武功抜群」 (徳川実記)
しかしながら、喧嘩両成敗につき、致仕して浪人となった。
その後、紀伊の徳川頼宣がこの話を聞き内々に扶助したが、昌縄は去り、細川忠興に仕官した。
昌縄 享年48歳。
参考文献
徳川実紀 旗本 新見吉治著 吉川弘文館 寛政重修諸家譜
古地図史料出版(株) 通販可 電話0424-76-1525 FAX0424-77-7811

昌純の養子
昌
継
永
時の娘
昌
縄
義
継

永時
義継、昌縄の母
右
永時の正室
将軍綱吉の側用人の
柳沢吉保の伯母
母は武田24将土屋昌次の妹